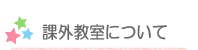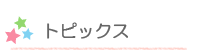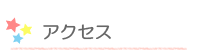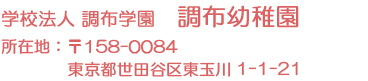ホーム > 園がめざすもの > 教育目標

園内研究報告
令和6年度 調布幼稚園 園内研究報告
1.テーマ
「体操」や「英語」の講師の指導に、教員も主体的にかかわり指導方法を学んだり、幼児理解を深めたりする。
2.テーマ設定の理由
専門の講師による指導を教師も一緒に体験することで、幼児と楽しさを共感し合い、その体験が普段の遊びにも繋がっていき、心と体の育ち、友達関係に繋げたいと考えている。
また、体操では年少時から、英語では年中時から継続して行うことで、年長になるにつれて、スキルが向上したり、聞き取れる単語が増えたりする中で、体操や英語の時間を楽しみにする姿がある。
教師は、短い時間の中でも幼児を引き付ける指導を行う講師の指導法を学び、幼児と一緒に主体的にかかわる方法を探ることで、「体操」や「英語」の時間がより有意義なものにしていきたい。
【体操】
入園した幼児の様子から、気象状況の影響もあり公園で遊んできた体験が少ない傾向が見られる。
また、戸外遊びの体験不足から、幼稚園でも空間感覚がつかめずドアにぶつかり転んだ時に手が前に出ずに顔面を打つなどの怪我もある。
本園では、遊びを通して体を動かす楽しさを個々の発達や年齢に応じて、体を思い切り動かして楽しむことで心も解放し、健康な心と体をはぐくみ生きる喜びを味わえることを目指している。
年少児から継続して行うことで、年長児になるに連れて、自分のめあてに向かって挑戦する心やクラスや学年などで協力して一つのことを成し遂げる達成感や満足感を味わい豊かな心と体作りも目指している。
【英語】
グローバルな時代への移行に伴い、日常会話の中にも英語が溶け込んでいる。海外旅行、インバウンドでの外国人との交流、将来、海外との交流を伴う仕事に就く可能性など、英語などの外国語はもはや必須言語となっている。
幼児期にネイティブの講師による英語に親しむことで、英語への関心を高めたり、英語を使う喜びを感じたりして欲しいと願っている。
また、幼児期に楽しく英語に触れることを通し、海外への関心も高まることを期待している。
3.ねらい
【体操】
●体を動かしながら友達とのコミュニケーションを図り、体を動かす楽しさを味わう。
●専門の講師に体操の指導を受けることで、年齢に応じた体や物の使い方及び体の部位や物の名称を知り、運動することを楽しむ。
●自分なりのめあてをもったり、挑戦したりする中で判断力や集中力、持続力を身に付け、達成感や充実感を味わい、スキルの向上に繋げる。
【英語】
●歌や踊りを通じて友達とのコミュニケーションを図り、英語に親しみをもつ。
●ネイティブの講師による英語指導の中で英語や外国の文化について知る。
4.活動スケジュール
【体操】
●3歳児と4歳児クラス 4月から2月まで月に1回から2回程度実施
3歳児合計 14回実施 活動時間1クラス30分
4歳児合計 16回実施 活動時間1クラス35分
●5歳児クラス 毎週金曜日(園行事が入っている場合は除く)
5歳児合計 28回実施 活動時間1クラス40分
【英語】
●4月から2月まで月に1回から2回程度実施(合計18回)
●活動時間は1クラス20分
6.まとめ
・活動の「ねらい」と、使用する物的環境の意図を活動前に担任と講師が打ち合わせてくことで、講師の動きの意図が分かり、担任も子どもたちの動きを見てやらない子やうまくいかない子への援助することができる。
また、担任個人の力量に左右されないようにするためにも、講師との打ち合わせや連携は大切である。
・活動の中で、講師〈担任〉との応答性による信頼関係が大切と感じた。
・体操では、担任にとっても、講師による実践指導はとても参考になりその保育に生かせる遊びや運動を学ぶ貴重な機会となっている。
・年間を通して活動に取り組むことで、様々な体の動きを柔軟にしていくこと、子どもたちの物の名称や体の部位の認知、どこから取り組むのか、どこをどうやるのかを判断したり、決定していく力や集中力、
持続力など「ねらい」に掲げていることが育っていくと感じた。
・参観日には講師が保護者に活動の意図を話すことで、正課の体操と日々の保育とのつながりが保護者にも伝わった。
・講師が子どもたちの姿に応じた言葉がけを担任も同じように声掛けして、実際に講師や担任がやって見せたりすることで、やる気を引き出したり、コツが分かったりする。
・英語では、担任は幼児の行動をサポートする援助や単語を日本語化して分かるようにしていくことがやる気に繋がるため、幼児の姿、不安な様子を見逃さないことが大事である。
また、講師の意図を汲み取り、子どもに伝わるように、しっかり声を出して補足をしたり、一緒に盛り上げたりしていると幼児の意欲に繋がり、理解が高まることが分かる。